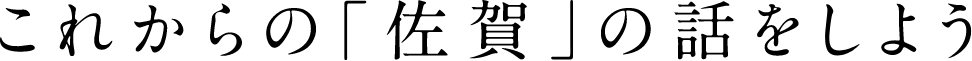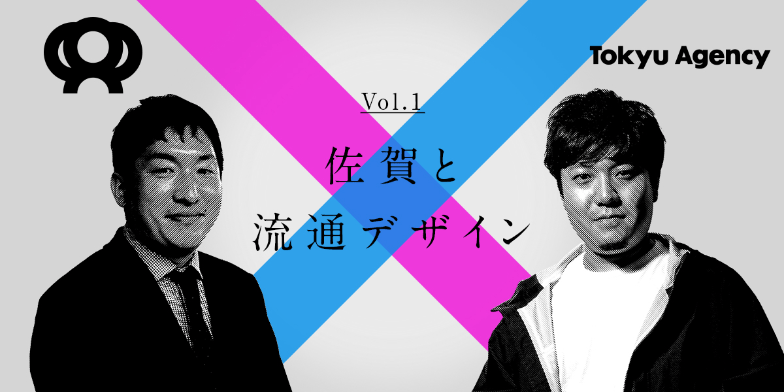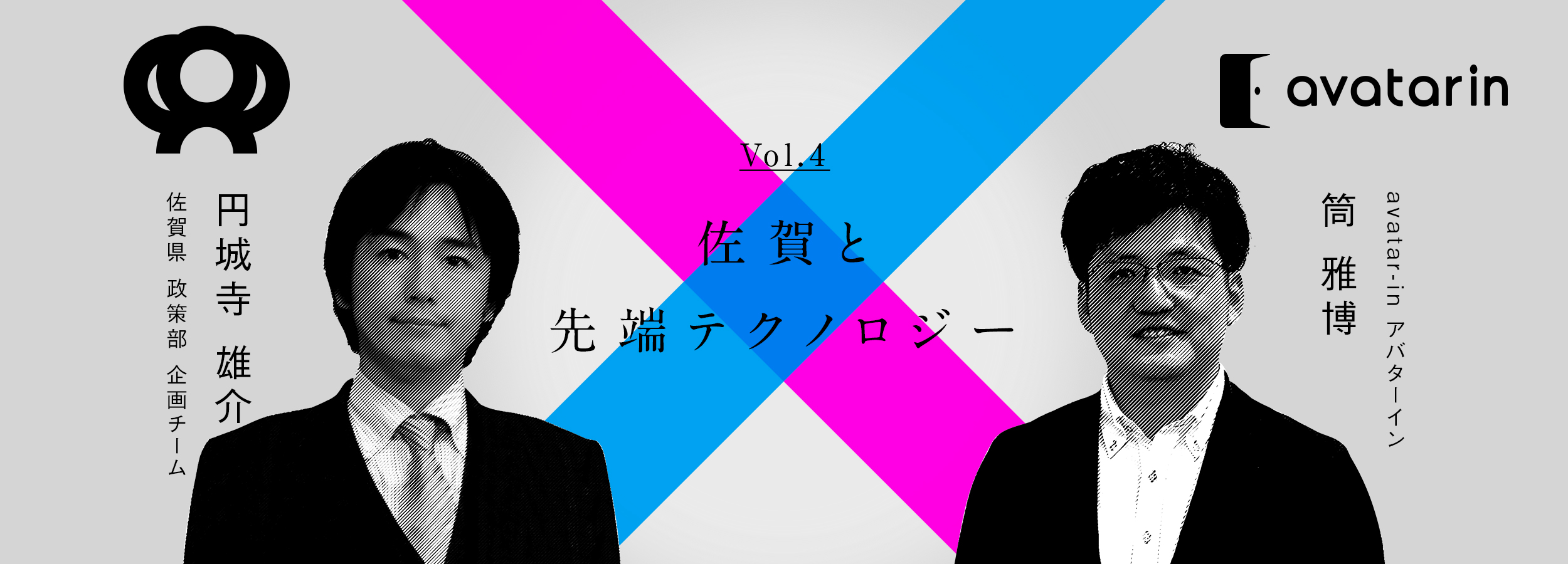

アバター技術で、地方自治体の課題解決に挑む。
2020年、コロナ禍により佐賀県内の医療機関での面会が全面ストップ。入院患者とその家族が対面できないという問題が発生した。そこで佐賀県庁は、ANAホールディングス発のスタートアップ企業のアバターイン社とタッグを組み、佐賀大学医学部附属病院にて遠隔操作型ロボットを活用した実証実験をスタート。リモートでの面会をスピーディに実現することに成功した。発案したのは、県庁職員の円城寺氏とアバターインの筒氏。常に革新的な取り組みに挑む2人に、プロジェクトの背景やこれからの佐賀のあり方について話を聞いた。※円城寺氏のインタビューは2020年度に実施したものです
円城寺 雄介
佐賀県庁 政策部 企画チーム/総務省地域情報化アドバイザー(※2021年4月からJAXAへ出向して、宇宙×地方創生を担当)
1977年生まれ。2001年に佐賀県庁へ入庁。全国で初めて佐賀県内の全救急車にiPadを搭載し、新たな救急医療情報システムの構築を図り救急搬送時間の短縮化に成功。佐賀での取り組みを全国に広げ、救急医療の変革に尽力。その活躍ぶりが多方面で評価され、MCPCアワード「グランプリ・総務大臣賞」、全国知事会「先進政策大賞」などを受賞。著書に「県庁そろそろクビですか?」(小学館)
筒 雅博
アバターイン ソリューション部 シニアマネージャー
1987年生まれ。国の研究機関である理化学研究所を経て、2020年アバターイン入社。ソリューション部所属。「物理的距離と身体的距離をゼロにする」というミッションのもと、アバター技術のインフラ化を目指して様々なイベントや企業・地方自治体とのコラボレーションを実施。
PROFILE
※掲載されている情報は取材当時のものとなります。
県庁職員とスタートアップ社員。 出会ったその日に意気投合した2人。
円城寺
昨年から筒さんとお仕事をさせていただいておりますが、アバターインさんってかなり新しい会社ですよね。
筒
はい。弊社は、遠隔操作型アバターロボットとそのアバター技術を用いたプラットホームを提供するANAグループの会社で、「物理的距離と身体的限界をゼロにする」をコンセプトに、昨年の4月に創業したばかり。いわゆるスタートアップ企業です。当社のプラットフォーム「アバターイン」を駆使すれば、どんなに離れた距離でも誰もが繋がることができるんです。
円城寺
遠隔操作ロボットってこれからの新しい社会インフラですよね。リモートで水族館を訪れたり、ショッピングをしたり、あらゆることが遠隔で可能になるってすごいですよね。
筒
ありがとうございます。WEBブラウザから「アバターイン」にログインし、モニターに自分の顔が映る遠隔操作型アバターロボット「newme」をリモートで操作する仕組みを構築しました。「newme」はタイヤが付いた可動式なので、離れていても様々な移動が可能です。
円城寺
私は今まで県内の全ての救急車にiPadを導入してリアルタイムで空いている病床がわかるようにしたり、高性能カメラを搭載したドローンを使って上空から救急患者を捜索できるようにするなど、テクノロジーを積極的に導入してきました。だからアバターという技術にものすごく可能性を感じました。ゆくゆくは医療現場にロボット技術も取り入れたいと考えていたので、すぐに御社に問い合わせのお電話をしました。すると筒さんがすぐ県庁に出向いてくださって、「なんてフットワークの軽い方なんだ!」と感動しました。
筒
お問い合わせいただいて嬉しかったですから。私も驚いたのは、県庁からの帰り際に円城寺さんがわざわざバスの乗り場まで送ってくださったこと。あまりそういった方はいらっしゃらないので、「佐賀県はなんだか他の地方自治体とは違うぞ」と思いました。
円城寺
互いにシンパシーみたいなものを感じたのですね。私自身、筒さんと今後のビジョンなどを熱くディスカッションできたので、これなら一緒に色んなことに挑戦していけると確信しました。
県内病院でアバター技術の実証実験。 患者と家族のリモート面会が可能に。
円城寺
筒さんが佐賀にいらして実際に「アバターイン」を体験させてくださった時、「これはコロナ禍の救世主になる!」と思いました。
筒
確かにこの情勢で、アバター技術が貢献できることは沢山ありますね。
円城寺
全国的にそうかもしれませんが、佐賀の医療機関では新型コロナウィルスの影響で患者さんと家族の面会が全面的にストップしました。そうすると患者さんは孤独になるし、家族も不安になる。「私は、誰かが困っているとき、誰かが泣いているときにこそ、人類の英知であるテクノロジーの力を使うべきだ」と強く思っていますので、アバターインさんのお力を借りることができて本当に良かったです。
筒
面会は、入院している方が病気や怪我を克服する上で、患者を元気付けるための重要なものであると思っています。アバター技術であれば、非接触でコロナでも面会ができることにいち早く着目した円城寺さんはさすがだなと感心しました。
円城寺
いえいえ。それで遠隔操作型ロボットを、救急車iPadやドクターヘリ導入を一緒に進めた、盟友・阪本雄一郎教授がいる佐賀大学医学部附属病院の高度救命救急センターへ試験的に設置していただきましたね。
筒
面会に行きたい人がアバターインのプラットフォームにログインし、現地(病院)にあるロボットを操作するだけなので使い方はシンプル。導入するハードルは低いと思います。また、たくさんの企業がロボットを開発しており、病院の中でロボットが活躍できる範囲は広いと思います。
円城寺
佐賀大学では、面会ロボットだけでなく、人と人との接触を避けられる自動消毒や配膳用のロボットも動き回っていて、近未来の病院をみているようなんですよ。
航空会社が、 アバター事業を始めたわけ。
円城寺
改めてアバター技術ってすごいなと驚きました。患者さんやその家族から「声が聞けて嬉しい」「表情がちゃんと見れて良かった」と多くの喜びの声をいただき、本当に導入した甲斐がありました。
筒
そう仰っていただけて、我々としても大変喜ばしいです。
円城寺
患者さんが不安な時に家族の声を聞いたり、家族も患者さんの姿を目で確認することは、計り知れない効果があると医療従事者から伺っています。すごく可能性に満ちた技術だと思うんですけど、そもそもなぜアバター事業を始めたのですか?
筒
実は、弊社の母体が航空会社であることが関係しています。これはエビデンスがあるのですが、エアラインを利用している方は、全世界の人口のわずか6パーセントなんです。
円城寺
飛行機を利用する人ってそんなに少ないんですね!考えたこともなかったですけど。
筒
利用されていない94パーセントの方達に対して「移動する喜びや飛行機に乗る楽しみ、移動した先で新しい人や文化に出会う醍醐味などをどう感じてもらうか?」を考えた時に、色々な障壁が見えてきました。時間がない、コストが高い、ハンディキャプがある、そもそもそのエリアに空港がない、などです。
円城寺
なるほど。当たり前のように飛行機を利用していましたが、世界的に見るとまだまだハードルが高いんですね。
筒
はい。そういった課題を解決するためにはどういう技術が必要なのかを突き詰めた結果、瞬間移動ができないかというのを考えたがきっかけです。IoTが発達している今、情報空間上で自分があたかもその場所に行けるような技術があれば、それは瞬間移動の一つと定義できるのではないかと思います。
円城寺
すごく腑に落ちました。「移動」をビジネスにしている企業だけあって、すごく説得力を感じますね。ビジョンが太いので、あれだけの先進的な技術を開発できているのも納得です。
地方自治体の抱える問題は、 アバター技術で解決できる。
円城寺
こうしてお話を伺うと、我々のような地方自治体が抱える問題が、アバターによって一気に解決されるかもしれませんね。
筒
ええ。アバター技術は基本的に場所を選ばず導入できるので、ショッピングや観光、子守りさえも遠隔でできてしまいます。
円城寺
そこまでいくと、もうリアル版「どこでもドア」みたいな感じですね。
筒
まさにおっしゃる通り。我々は「物理的距離と身体的限界をゼロにする」を掲げています。単純に相手とのリアルな距離をアバター技術によってゼロにする。高齢者やハンディキャップをお持ちの方は移動すること自体が困難なので、そのハードルをゼロにする。このようなことができれば、世界中の多くの人の人生をもっと充実させることができます。
円城寺
我々のような自治体がアバターを本格的に導入することによって、少子高齢化という深刻な地域課題を解決できるようになるかもしれませんよね。
筒
そうですね。例えば自治体さんが、アバター技術を使うことで、世界中から魅力的な人を集めてコラボレーションすることもできますし、関係人口を爆発的に増やすことができ、人口のあり方すらも変えることだってできるはず。そういった日本中の社会問題を解決するためにも、我々は日々、アバターの可能性を模索しています。
フロンティア精神に満ちた 佐賀人のDNAとは。
円城寺
今までのお仕事やお話を通して、我々とアバターインさんはスタンスがかなり近いんじゃないかと勝手に思いました。熱量が近いと言うか。
筒
私も同感です。ありがたいことに「アバターイン」や「newme」の導入依頼は多いのですが、円城寺さんのようにその技術を深く学んだり、それを使ってどう課題解決をするかまで考えている人は中々いない。先ほどの遠隔操作型ロボットを使った面会は、まさにそうです。円城寺さんも、その周りの方々も熱量が非常に高く、それを周囲の人達に広げていかないとああいった良いチームにはなりませんよね。
円城寺
ありがとうございます。県庁で私と一緒にテクノロジー活用を進めている、政策チームの井田康徳さんや溝口遥香さん、情報課の松永祥和さんがそうなんですけど、佐賀県民は真面目で挑戦的な気質。その理由は、佐賀の歴史に起因していると思うんです。150年前、幕末の佐賀藩は、常にチャレンジをするスタンス。当時は西洋文化の大砲や黒船などをほとんど見たことがない状況下で、自分達で大砲や蒸気機関車を作ってしまいましたからね。
筒
佐賀県民のDNAには、フロンティア・スピリッツが組み込まれているんですね。ある意味、江戸幕府よりも進んでいたんじゃないかと。
円城寺
まさにその通りで、大陸に近く、江戸時代はオランダなどの西洋文化と触れられる出島がある長崎に隣接しているという地理的な状況からも、佐賀県民の目線の先は常に外の世界に向いているんです。常に自然に変化し続けられるのは、佐賀県民の大きな強みだと思います。
筒
そんな県民性だからこそ、未来の佐賀がどんな県になっているのかすごく楽しみです。先進的な挑戦を実行しやすいユニークな土地なので、全国の参考事例となるような取り組みができるんじゃないですかね。
より良い世の中をつくるためには、 同じ志を持った仲間が必要。
円城寺
筒さんが今後目指すものって何ですか。
筒
大きく2つあります。円城寺さんも同じ考えかと思いますが、1つは佐賀県さんと一緒に「宇宙×アバター」事業に挑戦したい。当社で過去に行っていた時期がありますが、宇宙空間にアバターを搭載したカメラを飛ばして、リモート宇宙観光を定着させたいです。
円城寺
簡単な操作で自由に視点を切り替えられるでしょうから、誰にでも気軽に楽しめそうですね。
筒
もう一つは、先程も挙がりましたが、アバターを次世代の社会インフラにすること。佐賀県のみならず、過疎化・高齢化は日本の社会問題なので、アバター技術で解決したいです。
円城寺
少子高齢化でひとり暮らしの高齢者の方が増えてますし、さらにはコロナ禍で、外に出かけて誰かとコミュニケーションをする機会がどんどん失われていますもんね。
筒
はい。そういった問題をテクノロジーの力で挽回していきたいです。地域間での教育格差も解決できると思います。円城寺さんの今後目指すことは?
円城寺
医療現場をはじめとした地域の課題はまだまだ山積みなので、これからも色々なテクノロジーを取り入れて解決してきたいですね。さらには5年以上前から佐賀から宇宙分野への進出を目指しています。そのためにも、我々と同じ志を持った人材がもっともっと必要です。
筒
何をするかも大事ですけど、誰とするかも同じくらい大切ですよね。円城寺さんから見て、佐賀県庁さんにはどんな人が向いていると思いますか?
円城寺
そうですね。佐賀県庁というか、公務員全般に求められる人は、現場の人達のリアルな声に真摯に耳を傾けて、現場の課題をひとつひとつ解決して、自分のことよりも社会を良くする覚悟のある人、つまりは「義」がある人。そして「想像力」のある人ですね。担当している仕事が、誰のためにどんな風に役に立つのか。評価を他人や組織に求めるのではなく、自分が何をしたか。そこを実直に考えられる人は、同じ方向を向いて佐賀県、ひいては世の中をより良くできると確信しています。そういった同じ志を持った人と繋がるためにも、筒さんと一緒に挑戦を続けていけたらと思います。
筒
私も円城寺さんと繋がってから学ぶことが多く、仕事のやり甲斐がさらに増えました。より良い世の中をつくるために、一緒に頑張りましょう。